COLUMN
医院経営にまつわるコラムを定期的に配信しています。
医院経営にまつわるコラムを定期的に配信しています。
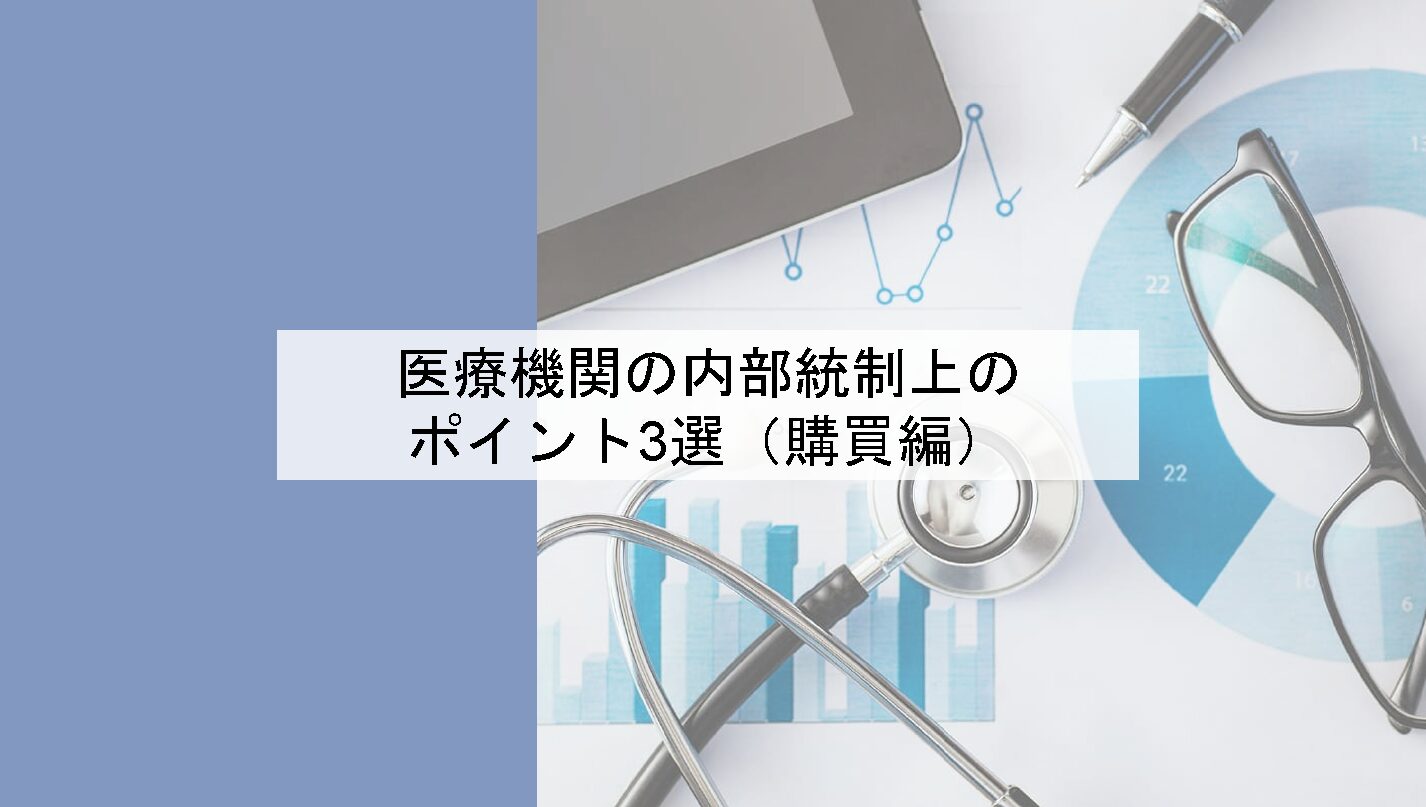
目次
内部統制とは、組織が事業活動を健全かつ効率的に運営するための仕組みを指します。内部統制を整備することで、例えば以下のような効果が期待されます。
内部統制を導入することで、業務プロセスの標準化と効率化が進みます。これにより、業務の無駄を減らし、リソースを最適化することができます。
内部統制は、法令や規則を遵守するための仕組、不正を防止するための仕組を整える役割も果たします。これにより、コンプライアンスリスクや、不祥事が発覚し医院の評判に傷が付くリスクを低減することができます。
内部統制は、特に上場企業を中心とした営利企業では広く浸透している概念です。しかし、医療機関においては、この概念が十分に普及していないのが現状です。また、営利企業における内部統制のベストプラクティスについては、インターネットや書籍で数多く紹介されていますが、医療機関では医療行為や医薬品の取り扱い、医療保険制度などに起因する業務の特殊性と複雑性があるため、十分なナレッジが蓄積されていないのが実情です。
本稿では、筆者が医療機関の監査などを通じて得た経験を基に、医療機関の内部統制におけるポイントについてお伝えしたいと思います。
診療科・診療内容によっては、高額な医薬品・特定保険医療材料が使用されることがあります。これらの医療材料の使用には、一般的に以下のリスクが生じると考えられます。
上記のリスクに対応するため、例えば以下のような内部統制を整備することが考えられます。
- 月初の在庫数量+該当月の仕入数量-月末の在庫数量で算出した理論消費量と、保険請求数量を突合し、異常な差異が生じていないことを確かめる。
例)N-1月にA医薬品を棚卸した結果、在庫が10個であった。N月にA医薬品を50個購入した。N月末にA医薬品を棚卸した結果、在庫が15個であった。
この場合、N月におけるA医薬品の理論上の消費量は10+50-15=45個となります。
別途集計したA医薬品の保険請求数量のデータと照合し、保険請求数量が45個であれば、消費したA医薬品が漏れなく保険請求出来ていることになります。
一方で、保険請求数量が25個であった場合は、理論上の消費量の45個との差分の20個について、差分が生じている理由が合理的かどうかを確かめる必要があります。
実務上は、薬剤部等からの払い出し時点と投薬時点のタイミングの差等の様々な理由により差分が生じることとなりますが、多額の差分が生じることについて合理的な理由が無い場合、請求漏れ、紛失や横領が疑われることとなります。
【留意点】
医薬品や診療材料の購買については、通常、以下のような業務プロセスになることが多いと思われます。
発注
現場担当者が直接発注あるいは、現場担当者の希望を取りまとめて購買部門が発注。
納品検収
商品の納入時に、納品された商品と納品書の記載内容(必要に応じて発注情報)が整合していることを確認。
請求(支払)
後日請求書が届き、請求書を基に業者へ支払。
ここで、請求(支払)フェーズにおいて請求額が商品の納品情報と照らして問題ないかどうかの検証が行われていないケースが意外と見受けられます。
当該検証を行わない場合、一般的に以下のリスクが生じると考えられます。
上記のリスクに対応するために、例えば以下のような内部統制を整備することが考えられます。
【留意点】
規模の大きい病院を中心に、SPD業者を利用している医療機関があると思われます。これらの業者の業務範囲は契約内容や仕様書によって様々ですが、急性期の病院を中心に診療材料の発注・納品(消費)・請求について次のような業務プロセスとなっているケースが多くみられます。
発注
各診療材料に定数を設定しておき、定数を下回るとSPD業者が当該材料を手配する。
SPD業者は当該材料を院内在庫(預託在庫)へ補充する。
※預託在庫型SPDの特徴としては、院内在庫へ材料が補充された時点では、当該在庫の所有権はSPD業者にあり、病院への請求が発生しない点が挙げられます。
納品(消費)
診療現場において材料を使用する際に梱包を開封します。この時梱包材に貼付されているバーコードシール等を剥がし、シール台帳に貼付します。
シール台帳はSPD業者により定期的に回収され、当該シール台帳に貼付されたバーコードシール等をバーコードリーダで読み込むことで、材料の消費情報がSPD業者のシステムに登録されます。そしてこの時点で当該材料の所有権がSPD業者から病院へ移転し、病院への請求が発生することになります。
請求
SPD業者は消費実績を基に請求書(及び納品書)を発行し、病院は請求書を基に支払を行います。
このような場合に、自院の担当者が納品検収を行った場合と比較して、請求内容の確認プロセスに次のような特徴があります。
そして、このような請求内容の客観的な検証が難しいという特徴を利用し、水増し請求やキックバック等の不正が行われるリスクが生じると考えられます。
上記のリスクに対応するため、例えば以下のような内部統制を整備することが考えられます。
昨今の人手不足の状況下では、日々の業務に加えて内部統制を実施することが困難な場合もあると思います。そのような場合でも、いきなり完璧を目指すのではなく、金額的に重要な取引に絞って検証を行ったり、数か月に一度の頻度で検証を実施したりするなど、リスクに応じた段階的な導入を検討することが大切です。こうした取り組みが、医療機関の健全な運営の一助となることを願っています。
G.C FACTORY公認会計士事務所は医療機関の会計監査において以下の強みを有しております。
ヘルスケア業界専門の当社は、医療・介護業界において長年の監査経験を有する公認会計士が担当いたします。よって、網羅的、かつ、無駄のないヒアリングや資料提供依頼などを行い効率的・効果的な監査を実施します。
公認会計士事務所による監査・内部統制対応に加えて、医院・介護施設運営における幅広いサービスを提供するG.C FACTORYネットワークを駆使し、コンサルティング部門より多岐にわたる経営改善提案が可能です。
拠点別管理等が複雑な会計管理が要求される医療機関の経理機能について、IT化等を通じて業務効率化・最適化を支援いたします。過去の支援先においては、経理部門などの業務工数が70%以上削減された病院・クリニックもございます。
業務効率化コンサルを行う当社は、自社の監査効率向上も常に行っており、監査における工数削減を実現しております。よって、監査報酬においてもコストパフォーマンスが高い対応が可能です。
弊社では介護施設・医療機関の法定監査経験が豊富な公認会計士が在籍しております。
本記事へのご質問や監査のご依頼は以下のリンクよりお気軽にお問合せください。
会計顧問のサービス案内はこちら➩https://tax.gcf.co.jp/service/accounting-tax-advisor/
法定監査のサービス案内はこちら➩https://tax.gcf.co.jp/service/statutory-audit/

筆者:澤田 将太(さわだ しょうた)
税理士法人G.C FACTORY
監査部 公認会計士
経歴:
公認会計士試験合格後、世界Big4のEYメンバーファームであるEY新日本監査法人にて、医療機関、上場企業、金融機関、IPOなどの幅広い会計監査業務や内部統制監査を担当。独立行政法人、医療法人、社会福祉法人、公益法人など様々な設立主体の医療機関の会計監査を経験。2024年7月にG.C FACTORYへ入社後現在に至る。
医院経営にまつわるお困りごとは
税理士法人G.C FACTORYへ。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お電話をいただいた場合は、担当部署を確認し、後ほど折り返しいたします。
